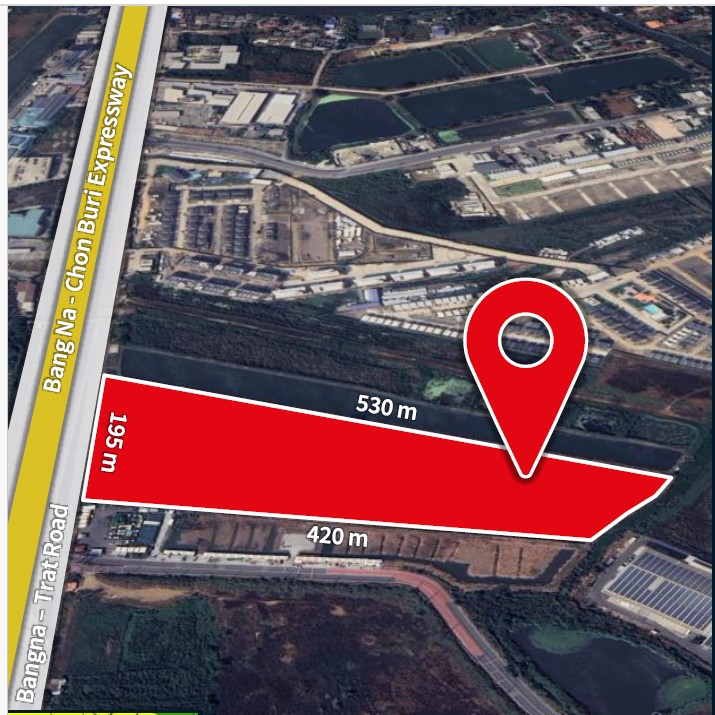【後編】2024年に過去最多の大量供給を迎える大阪オフィスマーケット
単年でみれば「過去最大」の新規供給がなされる2024年の大阪オフィスマーケットだが、かつて大量供給で市況が著しく悪化した「2013年の悪夢」が再び訪れるようなことはなさそうだ。【後編】となる本稿では、詳細なデータをもとに大量供給による賃料・空室率への影響を分析。今後の展望について紐解いた。
【前編】では、大阪オフィスマーケットにおける2024年の大量供給が「新規供給集中期」にあたり、前回の大量供給集中期と比較すると1年あたりの供給量は抑制されていることを紐解き、オフィス市況への影響は限定的にとどまるとの見方を示した。
【後編】では、大量供給による賃料・空室率への影響をさらに深掘りすると共に、今後の行方について考察する。
2024年の空室率は6.7%の見通し
図3:大阪オフィスマーケットにおける需給バランス(Aグレードオフィス) 出所:JLL日本
図3は大阪Aグレードオフィスの需給バランスの推移を示したものである。
大阪の空室率は景況感の変化による需要の増減よりも供給の増減の影響を色濃く受ける。【前編】にて新規供給動向について既述した通り、とりわけ近年は新規供給の大型化が進展しているために一定期間に供給が集中する傾向にあり、新規供給集中期に空室率が大きく上昇していることが明らかになった。
2008年の世界的な信用不安(リーマンショック)を端とする需要の減退期の空室率は2010年の6.5%で一旦ピークアウトし低下に転じたものの、2013年に5.4万坪の新規供給量(当時の過去最多)によって空室率は 9.5%に大きく上昇。過去最高の空室率を記録した。
2024年の新規供給量は8.2万坪で2013年を大きく上回り過去最多を更新するため、空室率も大幅に上昇し、2023年の 2.5%に対して4.2ポイント上昇の6.7%となる見通しである。
需給バランスの推移:本格回復は2028年以降
2024年の空室率は6.7%でピークとなり、2025年以降から低下に転じるとみられるが、 2027年までは5-6%台で推移し、本格的な回復は新規供給集中期後の2028年になると予測
さらにインサイトをお探しですか?アップデートを見逃さない
グローバルな事業用不動産市場から最新のニュース、インサイト、投資機会を受け取る。
今後の見通しの詳細は後述するとして、ここでは需要について考察する。
空室率は2013年にピークアウトして2019年にボトムを迎えるまで6年連続して改善した。この回復局面の需要動向は大別すると前期(2014-2016年)と後期(2017-2019年)に分けることができる。
前期(2014-2016年)の需給動向:リストラ型の需要拡大で賃料上昇に繋がらず
前期の需要動向は2012年末に打ち出されたアベノミクスによる効果によって、大規模の金融緩和や企業の業績回復の兆しの広がり、これまで慎重姿勢を崩さず腰の重かったテナントに動きが生まれた。
加えて、2013年に大阪では過去に類のない10%超(Aグレード以外も含む)の空室率を記録。マーケットは空室で溢れかえり、テナントが圧倒的に優位な状況であった。このため賃料が大幅に下落したことで割安感が生じ、テナントの動きを後押しし、需要拡大につながった。
前期の需要拡大はこうした背景だったため、テナントの移転動機は業容の拡大に伴う拡張や立地・ビルグレードの向上などは限定的であり、コストダウンを伴うリストラ型の移転が目立った。従って、空室率が低下局面であったものの、一部のビルを除けば賃料の上昇にはほど遠い状況にあった。
後期(2017-2019年)の需給動向:本格的な需要拡大期に突入し空室争奪戦に
一方、後期に入ると需要動向は一転し、本格的な需要拡大期になった。2017年からコロナ禍直前まで年々需要拡大の勢いが増していった。長期にわたるアベノミクス景気による企業業績の回復や労働需給のひっ迫によって、業種・事業規模を問わず、幅広いテナントの動きが拡大。
加えて、2018年に働き方改革を推進するための法整備が行われたことで、テナントの動きは活発になり、需要拡大につながった。テナントの移転動機は拡張、立地改善、ビルグレード向上が大半を占めていた。
しかし、こうした移転ニーズの受け皿となる空室はあっという間に枯渇し、2019年の空室率は0.1%(Aグレード以外を含めても1%未満)と深刻な需給のひっ迫を招いた。その結果、テナントによる空室の争奪戦が熾烈となり、希望するエリア・規模・スペックとはほど遠いビルであっても移転先を確保できないというリスクを回避するために、多くのテナントが“不本意”な空室を確保する動きが散見された。
コロナ禍の需給動向:需要低下ではなく供給要因で空室率上昇
その後のコロナ禍における需要動向を振り返ると、2020年4月に緊急事態宣言の発令後のほぼ1年間はテナントの動きが停止状態となった。減床の動きはコロナ禍の影響が直撃した旅行や商業関連のテナントからはじまり、大手企業を中心とするリモートワーク導入による一部返却がみられた。
しかし、当時、東京に本社を構えるIT企業や電機メーカー、外資系企業で数千坪の解約がなされるなどの報道が相次いだが、大阪ではこうした動きはほとんどなかった。
2020年と2021年の新規需要量はそれぞれ-800坪、-2,400坪に過ぎず、同年の新規供給量はそれぞれ6,200坪、5,700坪であった。従って、コロナ禍における大阪オフィスマーケットの空室率の上昇は需要サイドではなく供給要因によるものとみるのが妥当である。コロナ禍に新築ビルが決まらないのは、物理的に内覧もできない時期に移転を検討するテナントが不在であるため、致し方ないことである。
ポストコロナ(2022年以降)の需給動向:新規供給集中期に突入も需要は底堅い
そして、2022年から新規供給集中期へ突入した。「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」、「日本生命淀屋橋ビル」は、コロナ禍という逆風にもかかわらず、リーシング活動を活発に行えたことで賃料の大幅なディスカウントもなく、高稼働で竣工し、幸先の良いスタートを切った。
投資機会
今後の見通し
今後の見通しについて、2024年の空室率は6.7%でピークとなり、2025年以降から低下に転じるとみられるが、 2027年までは5-6%台で推移し、本格的な回復は新規供給集中期後の2028年になると予測する。
足もとの需要は底堅いものの、2024年の新規供給量8.2万坪は重く、空室率の上昇は避けられない。
論点は「高額賃料帯の供給増による需給のミスマッチ」
いくつかの懸念事項があるが、【前編】にて新規供給集中期(2022-2027年)について既述した通り、最も重要な論点は「新規供給ビルが優良ビルであるがゆえに賃料単価が高額であることで生じる需要と供給のミスマッチ」である。
いくら需要が拡大し、賃料負担の増加を許容するテナントが増えても、すべての供給量をまかなうことができるとは考え難い。この点に関しては、大阪にはなく東京固有の需要層となっている新興企業(IT関連)の本社や外資系企業の日本本社などに期待がかかる。こうした期待値を予測に織り込むことはできないが、大きく変わる梅田はこうした企業の受け皿となり得る環境を備えており、実現に向けて積極的なアプローチの継続を期待したい。
賃料の推移と今後の見通し
市場関係者からは「2013年頃に逆戻りするのではないか」といった声をよく耳にするが、杞憂に終わるだろう
図4:大阪オフィスマーケットにおける賃料動向(Aグレードオフィス) 出所:JLL日本
図4は大阪Aグレードオフィスの賃料(共益費込)の推移を示したものである。
大阪の賃料水準は伝統的に景況感の変化に対して、下落局面の感応度が高く、上昇局面においては低い。しかし、【前編】にて需要拡大期の後期(2017-2019年)における需要動向で既述した経験を経て、筆者は大阪の賃料水準は市況を反映して合理的に変化する“あるべき姿”になったと考えている。
依然として市場関係者からは「2013年頃に逆戻りするのではないか」といった声をよく耳にするが、杞憂に終わるだろう。主たる理由はオーナー以上にテナントの間に「賃料は上がる時は上がる、妥当な賃料上昇であれば許容する」ことが浸透したためである。
もし浸透していないのであれば、コロナ禍による需要減退局面…まとまった新規供給を控える今、新築ビルが大きな賃料のディスカウントもなく、また、既存ビルが空室を埋め戻す際の賃料条件がコロナ禍以前と同水準であるにもかかわらず、後継テナントが成約に至るようなことはないはずだ。
2008-2014年の賃料動向:リーマンショックで賃料暴落
大阪の賃料水準は2008年の世界的な信用不安(リーマンショック)の翌年の2009年に前年比-21.4%と下落した。Aグレードにおいては空室率が急上昇したわけではないが、Aグレード以外のビルを中心にコストダウンを急ぐテナントが投げ売りのようにオフィスを解約・減床していた需要の減退期であり、ここに大量供給期が相まって賃料の暴落を招いた。オフィス賃料は需要の減退と大量供給が重なるタイミングに最も下落する。
2017-2019年の賃料動向:本格的な上昇を記録
その後、2014年まで需要の底這いが続いたが、2015-2016年は対前年比で3-4%程度上昇し、本格的な上昇は2017年以降となる。2017-2019年の対前年上昇率は平均で8.3%、2019年は10.5%の上昇となった。
2021-2023年の賃料動向:コロナ禍の影響で下落局面へ
しかし、コロナ禍の2021年に対前年比-3.7%で下落局面入りとなったが、2022年、2023年と下落率は-3.1%、-1.9%に縮小している。
今後の見通し:2026年で底打ちの可能性
賃料動向を見極めるために重要な点は、新築ビルと既存ビルの動向と賃料帯(高額賃料、平均的賃料、低廉な賃料)別の動向を把握することにある。オフィス指標は空室率も賃料も新築ビル(大阪では大型ビル)の影響が大きく、こうした指標がメディアを通じて公表されることでマーケットのマインドが形成されやすい。マーケット状況が常態であれば過度に神経質になる必要はないが、現下のようにマーケットの過渡期においては、表面的な指標だけでは状況を見誤る可能性があるので注意が必要だ。
今後の見通しについて、2024年のAグレード全体の賃料は対前期比で-2.3%下落する。コロナ禍以降、下落率は縮小していたが、再び拡大に転じ、2025年もほぼ同水準の下落が続き、2026年は横ばい、2027年は小幅に上昇し、本格的な上昇は2028年以降になると予測する。
新築ビルは賃料弱含み、既存ビルは好調維持
新築ビルとの賃料格差が大きいため、既存ビルを割安に感じるテナントが多い
Aグレードオフィスの供給が進む大阪駅前エリア 画像提供:PIXTA
足もとの状況と今後の見通しについて補足する。
はじめに新築ビルと既存ビルの動向に大別すると、下落率は「新築ビル>既存ビル」となるだろう。新築ビルはゼロからテナント誘致しなくてはならない難しさ(=テナントに魅力的な条件を提供しなくてはならないケースが多くなる)があるためだ。
加えて、同時期に新築ビルが竣工(=競合ビルが増加)し、かつ高額賃料(=需要の絶対量が少ない)である。こうした“逆風”が相まって賃料は弱含みにならざるを得ない。
一方、既存ビルは軒並み高稼働を維持しており、空室を抱えるビルが少なく、競合ビルも少ない。また、新築ビルとの賃料格差が大きいため、既存ビルを割安に感じるテナントが多い。
こうした動向を各賃料帯別(高額賃料:坪2万円台半ば~、平均的賃料:2万円前後、低廉な賃料:~1.8万円が大まかな目安)にみると、Aグレード全体の賃料が2025年のボトムまでに4.6%下落するのに対して、高額賃料は 10-15%程度の下落、平均的賃料は横ばいから10%程度の下落、低廉な賃料は10%上昇から横ばいになると予測する。
なお、2028年以降の本格的な賃料上昇局面になった場合は高額賃料のビルがAグレード全体の上昇をけん引し、マーケットは正常化するだろう。
最後に
本稿では大阪のオフィスマーケットについて取り上げた。2024年を含む向こう数年間に焦点を当てて言及し、オフィス市況は需給バランス悪化、賃料下落を迎えることがメインとなり、ネガティブな印象を残したかもしれない。
しかし、2030年、2050年に向けて大阪は大きく変貌しようとしている。大阪の都市としてのポテンシャル、そしてその魅力、競争力向上のために必要な街づくりという長期的な視点に立てば、足もとで進行しているオフィスの新規供給は不可欠な要素、ポジティブ材料である。
今後もこうした見方を意識しながら大阪の不動産マーケットと向き合っていただきたい。
オフィスデータの定義
- 調査対象エリア:大阪市中心5区(北区、中央区、浪速区、西区、淀川区)のオフィス集積エリア
- グレード:Aグレード(延床面積:15,000㎡/4,538坪以上、基準階面積:600㎡/182坪以上、築年数:1990年竣工以降)、Bグレード(延床面積3,300-15,000㎡/1,000-4,538坪未満、築年数:1982年竣工以降)
【執筆者:JLL日本 関西支社 リサーチディレクター 山口 武】
連絡先 山口 武
JLL日本 関西支社 リサーチディレクターあなたの投資の目標は何ですか?
世界中にある投資機会と資本源をご覧下さい。そして、JLLがどのようにお客様の投資目標の達成を支援できるかお尋ねください。